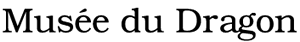-
latest news
Category
Archive
- 2024年April
- 2024年February
- 2024年January
- 2023年December
- 2023年November
- 2023年September
- 2023年August
- 2023年July
- 2023年June
- 2023年April
- 2023年March
- 2023年February
- 2023年January
- 2022年December
- 2022年November
- 2022年October
- 2022年September
- 2022年August
- 2022年July
- 2022年June
- 2022年May
- 2022年April
- 2022年March
- 2022年February
- 2022年January
- 2021年December
- 2021年November
- 2021年October
- 2021年September
- 2021年August
- 2021年July
- 2021年June
- 2021年May
- 2021年April
- 2021年March
- 2021年February
- 2021年January
- 2020年December
- 2020年November
- 2020年October
- 2020年September
- 2020年August
- 2020年July
- 2020年June
- 2020年April
- 2020年March
- 2020年February
- 2020年January
- 2019年December
- 2019年November
- 2019年April
- 2019年March
- 2019年February
- 2019年January
- 2018年December
- 2018年November
- 2018年September
- 2018年August
- 2018年July
- 2018年June
- 2018年May
- 2018年April
- 2018年March
- 2018年February
- 2018年January
- 2017年December
- 2017年November
- 2017年October
- 2017年September
- 2017年August
- 2017年July
- 2017年June
- 2017年May
- 2017年April
- 2017年March
- 2017年February
- 2017年January
- 2016年December
- 2016年November
- 2016年October
- 2016年September
- 2016年August
- 2016年July
- 2016年June
- 2016年May
- 2016年April
- 2016年March
- 2016年February
- 2016年January
- 2015年December
- 2015年November
- 2015年October
- 2015年September
- 2015年August
- 2015年July
- 2015年June
- 2015年May
- 2015年April
- 2015年March
- 2015年February
- 2015年January
- 2014年December
- 2014年November
- 2014年October
- 2014年September
- 2014年August
- 2014年July
- 2014年June
- 2014年May
- 2014年April
- 2014年March
- 2014年February
- 2014年January
- 2013年December
- 2013年November
- 2013年October
- 2013年September
- 2013年August
- 2013年July
- 2013年June
- 2013年May
- 2013年April
- 2013年March
- 2013年February
- 2013年January
- 2012年December
- 2012年November
- 2012年October
- 2012年September
- 2012年August
- 2012年July
- 2012年June
- 2012年May
- 2012年April
- 2012年March
- 2012年February
- 2012年January
- 2011年December
- 2011年November
- 2011年October
- 2011年September
- 2011年August
- 2011年July
カテゴリー別アーカイブ: 他
六百四十四話 Calla ?
九〇歳になられる友人の母親からなんか描いてと頼まれた。 「えぇ〜、なんかって何描くの?」 「これ!描ける?」 “ Calla ” の写真が携帯に送られてきた。 ちょうど都内の仏料理屋で昼食中だったらしい。 ちょうど目の前の食卓にたまたま生けてあったのが “ Calla ” だったようだ 。 そこそこ雑な注文だなぁと思いながらも。 「そりゃぁ、描けますよ、それなりの腕してんだから」 「号お幾ら?年金暮らしなんだから出来るだけお安くね」 都内の一等地で暮らし、昼から☆付の仏料理食ってる方の台詞とも思えない。 まぁでも、せっかくそう言っていただいたんだから描いてみることにする。 普段植物画を描く際は、実物を眺めて正確にそのかたちを映す。 だいたいが海辺の家の庭に咲く植物を描くのだが、あいにくと “ Calla ” は植わっていない。 画像検索してみたところ、花の写真ばかりで葉形や根の形状がいまいち不明だ。 解説文に、葉は里芋に似ており、根は球根上部より張ると記されている。 よく解らんが、葉は里芋を参考にして、tulip 球根の上部から根を描いてみるかぁ。 おぉ、筆を進めると、なんか “ Calla ” な感じに仕上がってきた気がしなくもない。 気に入っていただけるかどうかは知らんけど、とりあえずこれで筆をおく。 お待たせしました。 “ Calla ” みたいな水彩画をお送りいたします。 おばさん、いつまでもお元気で! … 続きを読む
Category : 他
六百四十三話 舞台 Odessa
今月の始め芝居を観にいく。 三谷幸喜作・演出 柿澤勇人 宮澤エマ 迫田孝也 出演。 “ Odessa ” 大阪公演初日。 中身もまったく知らず、ただ誘われるままに観た。 Odessa の地名から Ukraine 港湾都市のことで戦争に絡めた重たい話かと思ったけど違った。 そもそも舞台は、米国 Texas 州の Odessa という田舎町。 登場人物は、三人。 地元署の日系米国人女警官、鹿児島出身の殺人事件容疑者、偶然にも容疑者と同郷の通訳。 警官を宮澤エマさん、容疑者を迫田孝也さん、通役を柿澤勇人さんが演じている。 言語は、二つ。 日本語が解らない警官、英語が解らない容疑者、そして双方の言語が解る通訳。 真実は、一つ。 容疑者は、黒か?白か? 或いは、真実は白なんだけど実は黒? この後、福岡、宮城と公演は続くので、結末には触れないでおく。 舞台は、 Texas 州の幹線道路沿いにある diner 。 警官が、言葉の通じない容疑者を通訳を介しながら聴取していく。 その奇妙なやりとりが進む中、繰り広げられる三つ巴の心理戦を描く密室劇。 米国の Odessa と日本の鹿児島、Global だけど Local という設定がまた絶妙。 二つの言語と二つの文化が交錯する言葉の世界。 なにがどう面白いか? 伝えることが儘ならないけれど、確かに笑える。 膨大な台詞を巧みに回す三人の演者も凄いが、劇作家 三谷幸喜先生の着想も素晴らしい。 … 続きを読む
Category : 他
六百四十話 あけましておめでとうございます。
二〇二四年辰年が明けました。 DRAGON YEAR です。 無事、暖かく穏やかな良いお正月を迎えることが叶いました。 窓から眺める海峡。 風もなく、波もたたず、磨いた鏡のように輝いています。 今年一年こうあって欲しいと想えるような朝です。 これから過ごす一年が、皆様にとっても良き年でありますように。
Category : 他
六百三十七話 魔除け?
海辺の家の裏手で生まれて、今は丹波篠山の山里に暮らすおとこがいる。 おとこは猟師で、猪や鹿や熊など獣を獲るのが稼業だ。 若いが、猟師としての腕は良いらしい。 仲間内での呼び名は、カーリマン。 優れた体幹を備え、見た目も良く、講演などもこなす口も達者だ。 数年前にちょっとした縁で知りあった。 お陰で、海辺の食卓に山の幸が加わるようになる。 この鹿肉のソーセージをはじめ、春先の脂が少ない猪肉は炭火で焼いて焼肉に。 熊肉はそぼろにして丼物でと野趣な彩りを食卓に添えてくれる。 ある時、カーリマンから狩猟法について教えてもらう。 「食肉として用いるものは、全て罠猟と決めているんです」 「でないと、血が巡ってしまって臭みが残り旨くないんで」 「ってか、食肉以外で獲ることあるの?」 「そりゃぁ、頼まれれば駆除とかで、その際は銃で撃ちますけど」 「その後の毛皮と骨は、こんな風にして残します」 鹿と思われる数枚の毛皮と白い頭蓋を見せられた。 「ヘェ〜、綺麗なもんだねぇ、欲しいかも」 「マジですか、じゃぁ、今度、骨を傷つけず一発で仕留めてきますよ」 一年後、届いたのがこれ。 眉間中央に一発の銃痕、歯の一本も欠けていない完璧な鹿の頭蓋。 凄腕の成せる仕業で、仕上げも完全オーガニックなのだそうだ。 早速、海辺の家の壁に飾ってみる。 欧州では、鹿は崇拝の対象、神の化身、英雄的な探求の象徴として館に飾る習わしがある。 逆に、風水では、骨は死の象徴として嫌われるらしい。 まぁ、どっちも信じてないから問題ないけど。 丁度、隣家に暮らす嫁の幼馴染が、スワッグをクリスマス用に創って持ってきてくれた。 彼女は、人気のフローリストとして活躍している。 で、合体させたのが、これ。 これで、良いクリスマスになります。感謝!
Category : 他
六百三十六話 ゴジラ ー1.0
十一月十一日の夜。 骨の折れた右手を抱かえながら late-night screening の IMAX で観た。 “ ゴジラ -1.0 ” 内容は明かせないが、作品の素晴らしい仕上がりに魅せられました。 思えば、劇場で初めてゴジラを観たのは一九六四年の春だった。 “ モスラ対ゴジラ ” ゴジラを世に送り出した本多猪四郎監督と円谷英二特技監督が手を組んで制作された第四作。 以来、ゴジラは幼少期の記憶のど真ん中に居座り続けることになる。 昭和の時代、東宝ゴジラに続け!との大号令のなか他にも怪獣映画が制作された。 大映は “ 大怪獣ガメラ ” 、日活は “ 大巨獣ガッパ ” など。 父親は、当時活動屋として日活に在職していたのでガッパ制作側だった。 円谷監督の片腕だった渡辺明を特技監督として招聘し挑んだ日活唯一の怪獣映画。 封切初日、父親の冴えない顔を今でも憶えている。 「怪獣とか慣れへんことやるもんやないなぁ」とか言って、持帰ったポスターを眺めていた。 ガッパに限らず、過ぎゆく時代の中で他の怪獣達も産まれては消えていく。 だが、ゴジラだけは違った。 興行収益の紆余曲折はあったにせよ、昭和・平成・令和と生き抜いて今も銀幕に堂々と立つ。 いったいゴジラとは何者なのか? その答えのひとつが、作曲家 伊福部 昭先生によって創造されたあの鳴声にあるのだと思う。 ゴジラの鳴声は、一九五四年の初回作から大きくは変わっていない。 … 続きを読む
Category : 他
六百三十五話 骨折
ご無沙汰しております。 何故ご無沙汰しているかと言うと、利腕の手首を骨折したから。 先月からのギブス生活からようやく解放され、こうして blog でも更新してみる気になった。 骨折の理由は、あまりのくだらなさ故に口が裂けても言えない。 医者も手術か昔ながらの保存療法かで迷っていたが、後者を選んで自力治癒を目指すことにした。 ギブス装着期間は、左手頼みの不自由さはあったもののたいした痛みもなかったのだが。 問題は、外したその後からだ。 ちょっとの動きにも痛みが伴う。 医者から。 「痛かろうが、腫れてようが、とにかく動かしなさい」 と言われ、一枚の紙を渡された。 そこには、New York Yankees 松井秀喜選手の取材記事が記されていて。 二〇〇六年五月に手首を骨折して三ヶ月後に復帰するまでのいわゆる闘病記録だ。 医者は、松井選手もこんなに頑張ったんだから、おまえも頑張れよ的な趣旨だったんだろう。 だけど、そもそも、俺は、major leaguer じゃない! そして、めでたく治ったところで、 この右手が何億円も稼ぐことは今後おそらくない! 天と地ほどに motivation が違うだろう! なんの慰めにも励みにもならんわぁ! とはいえ自分が撒いた種で、悪いのは自身だ。 誰にも文句は言えない。 朝起きて、言われたとおり手首をグリグリまわしてみる。 痛ぁぁぁぁ!どんだけぇぇぇ!
Category : 他
六百三十一話 呪術廻戦展
呪術廻戦展を観てきた。 “ 呪術廻戦 ”に、こんなにも嵌るつもりもなかったし、嵌るとも想ってなかった。 しかし、あらゆる場面で精緻に描かれたこの眼の表現には 心底驚かされた。 原画を前にすると、その凄さがさらに迫って伝わる。 この角度から、この眼をこう描くとは。 到底、描けんなぁ。まさに特級術師だわ!
Category : 他
六百二十九話 妖怪ドロップ缶?
先日、車に置いておく喉飴を買おうと、普段あまり行かない離宮前のスーパーに行った。 此処は、駅前の店屋とは違い American Store 風のちょっと気取った店屋だ。 品揃えもホーム・パーティー用の惣菜とか、BIO 食材とか、ワイン類が目立つ。 客層は、小洒落た三〇代くらいの若い子供連れの夫婦が中心で、いつも繁盛 している。 屈んで、菓子売場の棚を探っていると。 突然、マスクを横から思いっきり引張られた。 それが半端な引張りようではなく、ゴムが伸びきるほどの勢いだ。 驚いて、左側を向くと。 綺麗な母親の肩に抱かれたこれまた美人になるであろう可愛い女の子がマスクの間を睨んでいる。 小さな人差し指はコの字に曲げられ、しっかりマスクのゴムが引っ掛けられていた。 驚いて、なんとか外そうと試みたけどなかなか上手くいかない。 すると、その二歳か三歳かの女の子が、こちらを睨みながら。 「なぁ、なぁ、妖怪ドロップどこ?」 知るかぁ!妖怪ドロップなんか!そんなことよりマスクを引っ張るな! 思ったけど、指からゴム紐を外すのに手一杯で口には出せない。 母親は、そんな状況であるにもかかわらず、気づかずゼリーの袋を眺めている。 娘が自分に訊ねているのだと思って気楽に応える始末だ。 「此処には、妖怪ドロップないんじゃないの」 途端、娘の顔がさらに険しくなった。 「妖怪ドロップ知らんの?なぁ?知らんの?」 もうマスクは、限界まで伸びきっている。 「知らんがなぁ!」 さすがに声をあげる。 その返事に気づいた母親の狼狽ぶりもひどかった。 「ええっ!うそぉ!やめてぇ!なにしてんのぉ!」 「すいません!ほんとに失礼しましたぁ!」 言いながら慌てて立ち去ろうとすると余計にマスクが引っ張られる。 娘に。 「お願いやから離してぇ!おかあさん、もう無理やからぁ!」 いや、無理なのは俺だから。 海辺の家に帰って、ヤツが執着していた “ 妖怪ドロップ ” なるものを検索してみた。 … 続きを読む
Category : 他