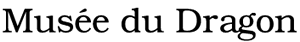Tuesday,February 03,2026

新しい節を迎えるために炒った大豆の古い皮を剥ぐ。
だから、旧作がどうであれ新作にすべてを賭ける興行師にとっても、これは大切な儀式なのだ。
幼い頃そう言い聞かされた覚えがある。
蠟梅薫る立春、二月四日の前夜に執り行う。

魔除けの大豆を用意して、鬼遣(おにやらい)の鬼役は隣家の犬に担ってもらうことに。
よもや自分が鬼にされているとは知らぬまま、鬼の面を被せられての強制参加。

海辺の家の出入口三箇所で、鬼は外、福は内。
願いを込めて豆を蒔く。
そうして、災いを退け、幸福を招いた後の晩飯。

献立は、 鰯の梅煮と恵方巻。
二〇二六年節分の厄除、平穏でありますように。
Monday,January 26,2026

仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙というらしい。
海辺の庭にもある。
なんの世話もしたことがなく、普段どこに植わっているかを気にすることもない。
それでも、冬の終わり頃になると寒風に揺られながらこうして庭のあちらこちらに咲く。
いろんな奴がいて。
なかには、花内側にある盃形の副花冠が白いのもいる。

洋の東西を問わず春を告げる花として世界中で愛される水仙。
“ 春一番 ” もうすぐ春ですねって、古るすぎてわからんかなぁ。
Friday,January 23,2026

Hamburger を食べたくなったら此処と決めている店屋がある。
駅舎の南階段を降りた目の前、砂浜にポツンと一軒建っている Hamburger Bar 。
“ Grateful’s ”
厨房に立っているのは、印度人と日本人。
客はというと、近隣に暮らす外国人達にも人気で、いつも半数くらいの席を占めている。
欧米、印度、中国、台湾、韓国や、どっかしら国からやってきたのだろう。
線路北側には Marist Brothers International School が在って、 学生達の姿も。
彼等の人種もさまざまで、Slang だらけの英語に時折神戸弁や広東語が飛び交う。
この界隈独特の Local Community 言語だ。
ちょっとした Chaos で、かつてこの地が居留地だった日の名残りかもしれない。
さて、肝心の Hamburger だが。
この店屋の一日は、 毎朝 Buns を店内で焼くことから始まる。
肉も塊で仕入れ、自らの手で挽いて Patty へと加工していく。
四種類ある Sauce は、一から手作り。
野菜もとびきり新鮮で申し分ない。
どれを注文しても間違いないのだが、僕はこの NY BLT Burger を気に入っている。
店内では、家の Living Room のような設で Sofa に腰掛けて過ごす。
冬、人気が少なくなった海岸から海を眺めながらの最高に旨い Hamburger 。
頬張っていると、どこか異国の寂れた港街にでもいるような不思議な気分にさせられる。
それは、異国情緒というような洒落たものからはほど遠い。
神戸の西端に残るどこか田舎臭くて、垢抜けもしない Local な日常の一幕に過ぎないのだが。
噂では、駅の逆側に北欧 Danish が営んでいる Denmark Hot Dog 屋もあるらしい。
店主は、Hansen さんというひとで、もう棲みついて随分になるという。
次は、散歩がてら Copenhagen 名物の Hot Dog でも食いにいこうか。
Monday,January 19,2026

久しぶりに服の噺をしてみたい。
同年代のおっさんから訊かれることがある。
歳をとったらおとこはどんな服を着れば良いのか?
まともに答えるのも面倒臭いので適当に返すことにしている。
もう、誰も気にも留めないし、見てもないんだから好きにすれば良いんじゃないの。
だけども、我が身の事となるとそうも言ってられない。
なかなかに難しい。
これは、私見なので真に受けずに聞いていただけるとありがたいのだが。
流行を意識して着飾るのはやめたほうが無難だろう。
高級 Maison の服で身を固めても、肥えた鴨が葱背負って歩いてるようにしか見えない。
では、Fast Fashion Brand ではどうか?
無難は無難だが、道ゆくただのおっさんでそれ以上でもそれ以下でもない。
前者は Waste (無駄) で、後者は Want (不足) だ。
また、この両者を組み合わせて着ることを自慢げに提唱する無能な Stylist もよくいる。
婦人服についてはわからないが、紳士服の領域ではそんなことはあり得ない。
高齢になればなるほど質感の統一は大事だと思う。
要は、Waste (無駄) は Want (不足) を補わないということだ。
では、何をどうすればいいのか?
ここで一番大切なのは服に対する愛着があるか?どうか?だ。
もし無ければ、これはもうこの時点で諦めてもらう他ない。
箪笥のなかを覗いてみてると愛着の有無がわかる。
愛着があるひとに限ってだが。
着倒してもう諦めて捨てるしかないほど着た挙句、それでも捨てられない服が数着あるはず。
Trench Coat だったり、M-51だったたり、Tweed Jacket だったりという感じで。
ひょっとしたら手編みの Cowichan Sweater という方もおられるかもしれない。
おそらく、それらは誰もが一度は目にしたことがある普通の ITEM だと思う。
しかし、それぞれのひとにとっての Archive であり原点ともいえる服。
今更、それらを引っ張り出して着ろとは言わないが、労を尽くせば市場で探し出せるだろう。
大枚を叩いてでも自身の原点であるとびきりの一着を再び手に入れてもらいたい。
その一着がお釈迦になる頃には、自分も棺桶で横になってると思えば安いもんでしょ。
後は、今の自分とその一着に合う他の ITEM を吟味するだけ。
気を衒わず、普通に、着心地と質を大切にして。
おとこは、おんなと違って化けるという才に恵まれていない。
おとこの装いは、良くも悪くも自身そのものを映しだす。
髪の毛がなくとも、瓜みたいなかたちでも、背が縮んでも、それらすべての三重苦であっても。
堂々と隠さず自分らしくあることが一番だと想う。
なんとかなりますよ、きっと。
Wednesday,January 07,2026

七日に七草粥を喰うと、無病息災・健康長寿の願いが叶う。
ほんとかどうかは、知らんけど。
値の張る Supplement は服用しないが、こういう安上がりの決まり事はとりあえずやっておく。
だから、冬至の柚子湯にも毎年入ったりもする。
芹・薺・五行・繁縷・仏座・菘・蘿蔔といった春の七草。
このうち庭で五種類くらいは採れるのだが、味・食感とも最悪で食えたもんじゃない。
なので、八百屋でちゃんとした草を揃えて買うことにしている。
炊き終えた七草粥を食籠によそって、縁側ですこし冷ます。
粥だけでは味気ないので、醤油をつけて炙った奥出雲の蕎麦餅を中に落として喰う。
こんな草粥が、思いのほか旨いから不思議だ。
Sunday,January 04,2026

忌明けの正月も三日がすぎて、新年の四日。
用意した御節料理もそろそろ尽きてきた。
我が家の祝膳。
口取り・焼き物・酢の物などは料理屋に注文する。
今年は、東門街で営む人気の Bistro “ HEEK ” にお願いした。
毎年決まった店屋というわけでなく、年によっては中華料理屋だったりもする。
ただ他はそれで良いのだが、大好物の煮〆だけは他人任せというわけにはいかない。
僕的には、煮〆さえあれば正月を迎えられるというほどだ。
筑前煮みたいな柔らかな食感は駄目で、充分な歯応えが欲しい。
箸上げがしづらいくらいに、ごろっと大きく。
具材それぞれの味が活きるように、できるだけ煮出しは薄味で。
蓮根・里芋・筍・椎茸・人参・蒟蒻・牛蒡の七種を、別々に煮る。
毎年、厨に立つ嫁にしてみれば。
“ じゃぁ、あんたが作ってみろよ!” となるのだが、機嫌を取りつつなんとかありついている。
そして、我が家の祝膳にはもうひとつ他家にはない決まり事があって。
それは、膳のどこかに偽りの一皿を仕込む事。
蟹のように見える蟹蒲鉾的な感じと思ってもらえれば良い。
嫁、渾身の Marine de saumon 。

これのどこが偽りなのか?
Caviar に見立てた “ とんぶり ” かと思うかもしれないけれど違います。
これは、正真正銘の蝶鮫の卵です。
偽りは、そもそも Marine de saumon ではなくて、ただの Tomato というのが正解。
正月早々、くだらない!
しかし、恒例のくだらない一皿を毎年楽しみにしている酔狂なひともいてこうして続いている。
画像を見た甥が訊いてきた。
「おじちゃん、これって偽りなんだろうけど旨いの?」
旨いわけないだろう!ただの Tomato の味で、それ以上でもそれ以下でもない。
で、これは、偽りのない本物。

元日に訪ねてきてくださったお客さんのお年賀。
牛腿肉の Roast Beef 。
明治期創業、神戸で知られた名店 “ 大井肉店 ” の逸品。
Roast Beef ってこんな旨かったかなぁ?
あたりまえだけど、やはり本物は違う。
おかげさまで、穏やかで食に恵まれた正月を迎えられました。感謝です。
Thursday,January 01,2026

二〇二六年一月一日。
あけましておめでとうございます。
隣人 Florist 師匠に、ああだのこうだの駄目だしを喰らいながら創ったしめ飾り。
今年は午年、それでも海辺の家では Musee du Dragon の Icon “ 龍 ” 。
とりあえず昇龍みたく撮してはみたけれど、ほんとうにやりたかったのはこれ!

柳の枝に餅をちいさく丸めてつけていきながら創る “ 餅花 ” 。
五穀豊穣を祈願する日本古来の正月飾りだ。
その “ 餅花 ” を雪に見立てて、奥に龍のしめ飾りを重ねる。
舞う雪に翔ぶ龍。
なにより縁起が良いこと半端ない。
師匠、ご指導ありがとうございます!今年もよろしく!
みなさまにとって、穏やかな良い年となりますように。
Wednesday,December 31,2025

二〇二五年一二月三一日。
大晦日ということで、今年も終わりです。
人生に正解か?不正解か?の答えがあるのかどうかは、知らないけれど。
兎にも角にもその時々やるべき事をやって、歳を重ねてきた。
で、結果どうだったかを問われると。
上々の仕上がり具合とまではいかないが、まぁ、こんなもんじゃねぇのといった感じでいる。
過ぎ去ったことをあれこれ考えてもしょうがないし、先はわからない。
そもそも、“ 反省 ” の二文字も、ついでに “ 志 ” の一文字も母親の胎内に置いてでてきたから。
明日が来ると信じて、今日を飄々として生きる。
二〇二六年もそうしていく。
今年一年ありがとうございました。
みなさん、良いお年を!
Wednesday,December 24,2025

二〇二五年十二月二十四日、今夜は Christmas Eve です。
今年は、隣人 Florist 指導の下、過去最大級の Wreath を嫁が創った。

隣家の葡萄棚から枝を切り出し、絡めて巻く。
Israel Grevillea Gold の葉、松毬、茶綿、Eucalyptus の実などを添わす。
色も形も茨の冠に似た大きな Wreath 。
もうひとつは。

同じく葡萄枝に、山帰来の紅色に染まった実。

食卓には、友人が贈ってくれた燭台。

鈴木玄太作の硝子器。
なかには、二〇世紀初頭に伊 Murano 島で創られた聖人の吹硝子像。
こんな感じで、二〇二五年の聖夜を迎える。
海辺の家で過ごす大切な一夜。
Hope you have a wonderful Christmas!
Wednesday,December 17,2025

海岸にある Burger bar 。
犬連れは外の席でと言われたので、冬空の下 Terrace に。
二、三日に一度はやって来る隣家の犬。
最近、俺の残り少ない時間がこいつに費やされていることに気づく。
まるで Time Eater だ。
長く生きた老人と産まれて間もない犬。
まぁ、隣同士で雄同士なんだから、助け合って仲良くやっていこうな。